ロハス工学からロハス学への進化を目指して
~ロハス工学の視点から考えるこれからの地域づくり~

11月2日(土)、市民公開講座『第12回ロハス工学シンポジウム』が開催されました。「ロハス工学からロハス学への進化を目指して~ロハス工学の視点から考えるこれからの地域づくり~」をテーマに、工学以外を専門とする社会学、介護、医学などの有識者を招聘しての基調講演のほか、日本大学の他学部や各地で地域づくりを進めるキーパーソンと日本大学研究者との間でパネルディスカッションを行いました。
工学部では、2007年より「ロハスの家研究プロジェクト」を始動させ「ロハス(健康的で持続可能な生活様式)」を工学で実現するための「ロハス工学」を基軸として研究を推進しております。今回のシンポジウムでは、ロハスの概念を「工学」に限らず「新たな分野」へ展開することを目指しており、「ロハス」のさらなる発展・可能性を探るきっかけとなることが期待されます。
 開会にあたり、はじめに根本修克工学部長(写真)よりご挨拶いたしました。根本学部長は本シンポジウムについて「専門分野を問わない学問、すなわちロハス工学からロハス学に発展させる礎を構築することが目的であり、それぞれの立場から地域づくりを果たすロハス工学の役割について意見や議論が展開されることを期待する」と述べました。続いて日本大学副学長である医学部の兼板佳孝教授が登壇し、日本大学と地域社会との連携について触れ、社会に役立つ研究成果をフィードバックし社会に貢献することが大学の重要な役割だと述べるとともに、本シンポジウムが有意義な時間になることを祈念しました。
開会にあたり、はじめに根本修克工学部長(写真)よりご挨拶いたしました。根本学部長は本シンポジウムについて「専門分野を問わない学問、すなわちロハス工学からロハス学に発展させる礎を構築することが目的であり、それぞれの立場から地域づくりを果たすロハス工学の役割について意見や議論が展開されることを期待する」と述べました。続いて日本大学副学長である医学部の兼板佳孝教授が登壇し、日本大学と地域社会との連携について触れ、社会に役立つ研究成果をフィードバックし社会に貢献することが大学の重要な役割だと述べるとともに、本シンポジウムが有意義な時間になることを祈念しました。
次に岩城一郎工学研究所長兼ロハス工学センター長より趣旨説明を行いました。岩城工学研究所長はこれまでのロハス工学の変遷を辿りながら、新たに設置されたロハスの森「ホール」について紹介しました。最後に書籍「ロハス工学」の一節を読み上げ、不変性、持続性、発展性を重要視しつつ、これからは工学以外との連携によりどこまでロハスを実現できるかという命題に移行していく中で、本シンポジウムがそのキックオフになるだろうと示唆しました。
次に、3名の有識者の基調講演を行いました。
『ロハス工学への期待~熊本・天草の地域づくりの実践から~』
日本大学客員教授/元NHK解説委員 後藤千恵
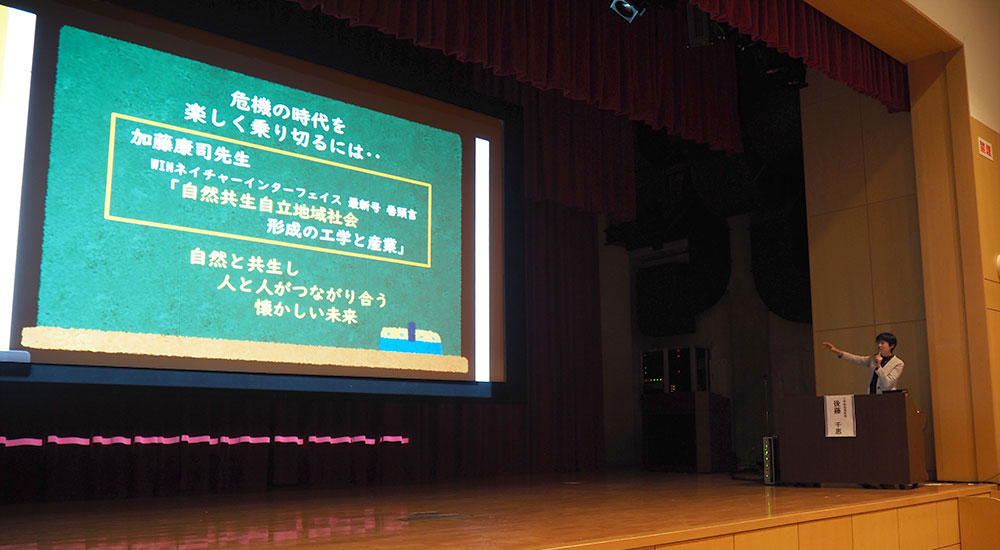
後藤氏はNHKを早期退職し、現在は熊本県天草市五和町の里山をコモンズ(地域の共有資産)として活用しながら、”懐かしい未来”の持続可能な地域社会づくりを目指す「一般社団法人 天草1000年の人と土の営み」で、自然の力を引き出し、人の力を引き出す取り組みに従事しています。森の活用やインフラの維持管理など実際の活動についていくつかご紹介してくださいました。そして地球が直面している危機について指摘し、この危機を乗り越えるためのバイブルとして書籍「ロハス工学」を推奨されました。一極集中の時代から地域が多極化する時代へ、工業主体の文明から農耕文明の時代へ、まさにロハス工学からロハス学が求められており、第二の維新を担う若者を育てることが大事だと諭されました。最後に、工学部生を対象とした天草インターンシップの実施について触れ、このシンポジウムが第二の維新の第一歩につながるよう期待を寄せていました。
『ケアする心をまちの文化に~鞆の浦さくらホームの実践~』
鞆の浦・さくらホーム施設長/羽田冨美江

ジブリ映画「崖の上のポニョ」のモデルになった広島県福山市鞆町に、2004年4月に開所された「鞆の浦・さくらホーム」。羽田氏は初めにこの映画について触れ、自然と人間の共生がテーマになっており、まさにロハスに通じるものだと伝えました。「鞆の浦・さくらホーム」は、年齢を重ねても障害があっても居場所となるまちづくりを目的に介護・福祉事業を展開しています。利用者・職員・地域住民が互いに顔が見える距離感で、まち全体で見守る仕組みづくりを行ってきました。次世代につなぐ取り組みとして、鞆こども園との連携、医療・教育機関との連携、就業事業所と子育て世代との連携について、具体的な事例をあげて紹介してくださいました。地域との信頼関係を構築し、地域に開かれた施設づくりを実現してきた経験を通し、「ケアする心をまちの文化に」していきたいと、その思いを強くされていました。なお、「鞆の浦・さくらホーム」は今年、日本地域福祉学会より地域福祉優秀実践賞を受賞されています。
『遠隔画像診断の実状』
日本大学医学部教授/岡田真広
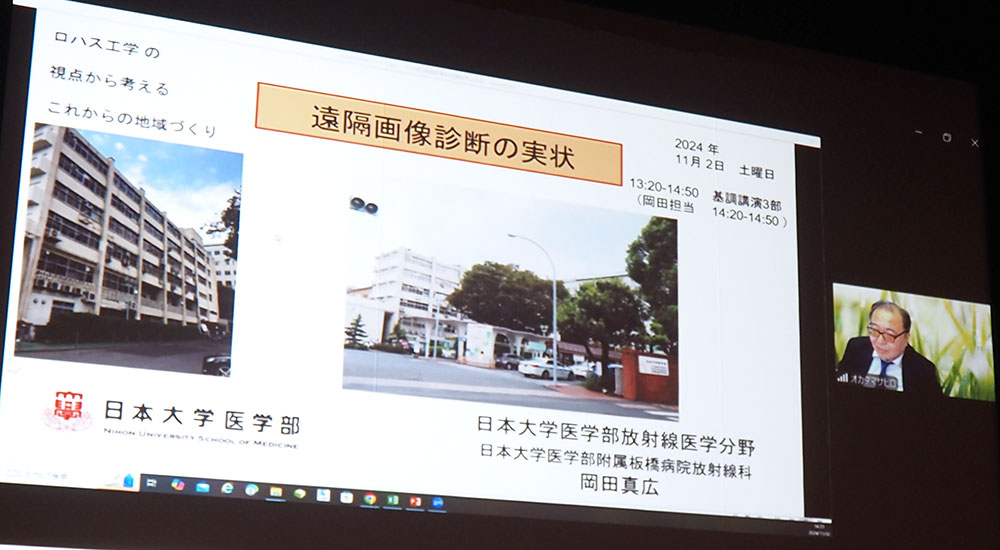
遠隔画像診断はICT情報通信技術を利用して、CT・MRI、核医学等放射線画像の全ての画像検査の読影や診断を実施した医療機関以外の場所で行う医療行為を指します。岡田教授は日本の遠隔画像診断の根底として、画像診断医(専門医)の人数が少なく、画像を撮っても初見(レポート)を専門に書ける人材が不足していることを指摘。しかし、ICTの発展により画像伝送による診断が可能になったことから、国内外いつでもどこでも遠隔画像診断ができるようになったと話しました。近年ではAIによる画像診断支援サービスも普及。一般企業型、大学病院系、専門医型など様々な遠隔画像診断センターも確立されました。遠隔画像診断の事例について、地域と大都市の病院がつながって緊急搬送から手術までの時間を短縮したり、医師同士がつながってPROMISE試験を成功させるなど、つながるツールとして遠隔画像診断が地域医療に大きな役割を果たしていることを示しました。
それぞれの地域での取り組みから、
これからの地域づくりの手掛かりを探る
続くパネルディスカッションに先立ち、パネリストからそれぞれの地域での取り組みについて話題提供がありました。

『NPO法人【たなぐら里山板橋キビタキの森】―活動紹介とロハス工学への展開を目指して―』
特定非営利活動法人たなぐら里山板橋キビタキの森副代表理事 大塚孝義
里山整備活動の継続性と後継者育成を主な課題として挙げ、解決に向けた様々なアプローチを検討している状況を説明。
『介護施設が運営する宿がまちに溶け込むまで』
鞆の浦・さくらホーム お宿と集いの場燧冶 管理人 羽田知世
宿と集いの場としての機能を持った施設を運営。まちの外と中をつなぐハブとなり、交流や活動が広がっていることを紹介。
『地域振興から見るロハス工学』
葛尾村地域振興課地域づくり推進係 経済産業省派遣 杉本誠
工学部との連携など、復興に向けた葛尾村の取り組みの中で地域コミュニティの再生や公共施設の管理運営について紹介。
『高大連携による新たなモビリティによるまちづくり』
国際関係学部国際総合政策学科准教授 矢嶋敏朗
日大三島高校の探究学習を活用し、バスの無人運転プロジェクトを実施。自治体も巻き込みながら若者主体で未来のまちづくりを推進。
『住民と共に守る!橋のセルフメンテナンス平田村モデル』
工学部客員研究員 浅野和香奈
長年、平田村で行ってきた住民主体型橋のメンテナンス。自治体で橋の維持管理を行うためのモデルとなり全国展開されている。
人と人、地域と地域をつなぐことが重要な鍵

左から)岩城一郎教授、浅野和香奈研究員、矢嶋敏朗准教授、杉本誠氏、羽田知世氏、大塚孝義氏
 話題提供後、コーディネーターとして建築学科の浦部智義教授が登壇し、パネルディスカッションを進めました。まずはパネリストの方々に、基調講演への意見や感想を伺いました。杉本氏は地域づくりにおいて「人」が大事になる点を踏まえ、どうすれば人を巻き込んでいけるのか後藤氏にアドバイスを求めました。後藤氏は、頼まれたことをどんどん引き受けて「つながる」ことを大切にしてきたと話すとともに、自治体に頼るのではなく、まずは自分たちの力で取り組む姿勢が大事だと伝えました。続いて矢嶋准教授からは地域の利害関係を上手く調整するポイントについての質問があり、対話を大事にし、全ての人がプレーヤーとして関わっていける仕組みを作っていくことだとアドバイスしました。
話題提供後、コーディネーターとして建築学科の浦部智義教授が登壇し、パネルディスカッションを進めました。まずはパネリストの方々に、基調講演への意見や感想を伺いました。杉本氏は地域づくりにおいて「人」が大事になる点を踏まえ、どうすれば人を巻き込んでいけるのか後藤氏にアドバイスを求めました。後藤氏は、頼まれたことをどんどん引き受けて「つながる」ことを大切にしてきたと話すとともに、自治体に頼るのではなく、まずは自分たちの力で取り組む姿勢が大事だと伝えました。続いて矢嶋准教授からは地域の利害関係を上手く調整するポイントについての質問があり、対話を大事にし、全ての人がプレーヤーとして関わっていける仕組みを作っていくことだとアドバイスしました。
 次に鞆の浦・さくらホームの取り組みに関して、大塚氏が従来の介護施設の範囲を越えたまちづくりを発想した理由について尋ねると、羽田(冨)氏は介護される立場の方への地域の人の見方・考え方を変えたいという思いから施設を開設したのだと説明しました。大学院生の時に鞆の浦・さくらホームで研修を受けたという浅野研究員は、地域全体でケアする体制をどのように築いていったのかを興味深く聞きました。羽田(冨)氏も頼まれたことは断らず地域との信頼関係を築いてきた結果、15年ほど経ってようやく協力してもらえるようになったと話しました。
次に鞆の浦・さくらホームの取り組みに関して、大塚氏が従来の介護施設の範囲を越えたまちづくりを発想した理由について尋ねると、羽田(冨)氏は介護される立場の方への地域の人の見方・考え方を変えたいという思いから施設を開設したのだと説明しました。大学院生の時に鞆の浦・さくらホームで研修を受けたという浅野研究員は、地域全体でケアする体制をどのように築いていったのかを興味深く聞きました。羽田(冨)氏も頼まれたことは断らず地域との信頼関係を築いてきた結果、15年ほど経ってようやく協力してもらえるようになったと話しました。
3つめの講演の遠隔治療を題材に、浦部教授は福祉施設を運営する立場から医療に期待することについて羽田(知)氏に意見を求めました。羽田(知)氏は遠隔医療を希望の光だと言い、医師との情報共有も含め過疎地域にとって遠隔医療は重要だとしました。続いて、各パネリスト同士や会場の参加者との意見交換の時間を設けました。住民と行政との連携や自治体同士の連携、県・国との連携などに話題が発展しました。互いの講演や話題提供から、それぞれの地域にも活かしていける取り組み方や考え方があり、大変有意義な時間になったようです。浦部教授は地域の取り組みもできるところから始めていけば無理なく持続でき、やがて大きな形に発展していくのではないかと示唆しました。
最後に、岩城教授がロハスの本質について触れながら、今後の展望について述べました。無理なく心身ともに心地よく生活することがロハスであり、よりよい社会を実現するために人と人、地域と地域をつなぐことの重要性を強調しました。本シンポジウムの狙いは、参画いただいた各地域の方々がつながることはもとより、大学内の人と人とのつながりを強固にし、ロハス工学からロハス学へ発展させることだとし、その一歩を踏み出すよい機会になったとシンポジウムを振り返りました。
 閉会にあたり、挨拶の壇に立った工学研究所次長の加藤隆二教授は、シンポジウムを通してロハス工学が多方面に広がっていること、アクティブな活動が成果を生むことを実感したと述べました。最後に参加者の皆さまへの御礼の言葉を持って、幕を閉じました。
閉会にあたり、挨拶の壇に立った工学研究所次長の加藤隆二教授は、シンポジウムを通してロハス工学が多方面に広がっていること、アクティブな活動が成果を生むことを実感したと述べました。最後に参加者の皆さまへの御礼の言葉を持って、幕を閉じました。
参加した学生からは、「ロハスについて学ぶ機会はなかなかないので、勉強になりました」、「工学の視点だけでなく、観光の視点など多角的に見れたのが面白かったです」、「建築を学んでいて、幅広い知見が得られたのは収穫でした」と話しており、学生にとっても貴重な学びの場になったようでした。
「ロハス工学」から「ロハス学」へ。どのように進化していくのか、今後の動向に期待も高まっています。
