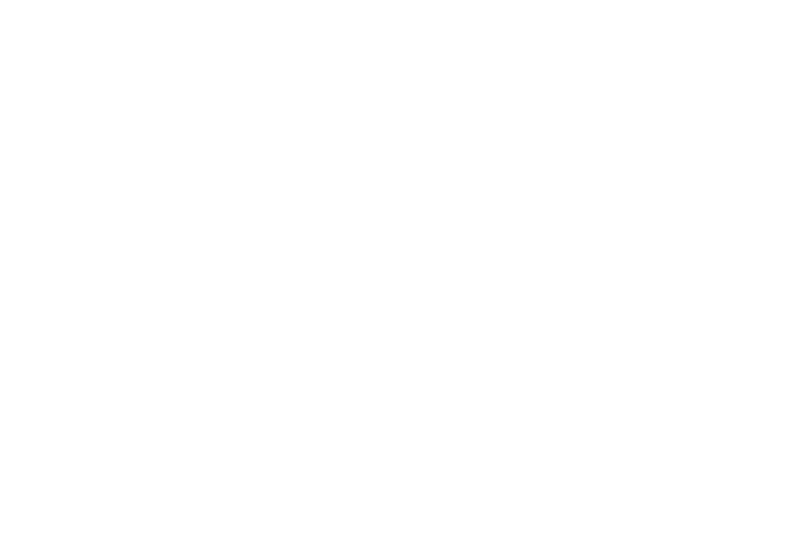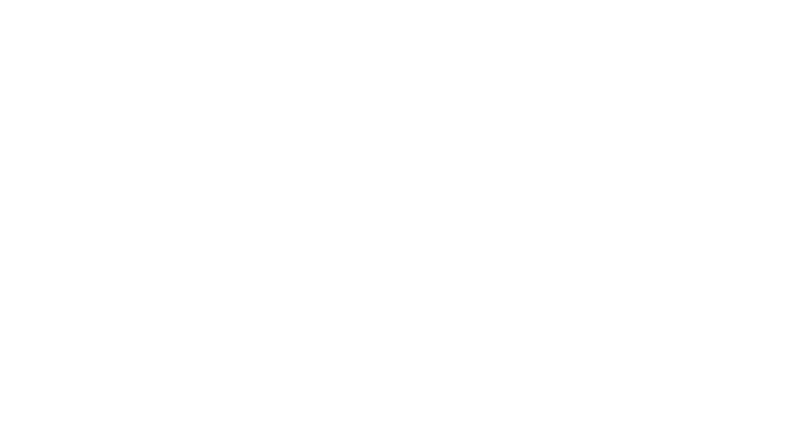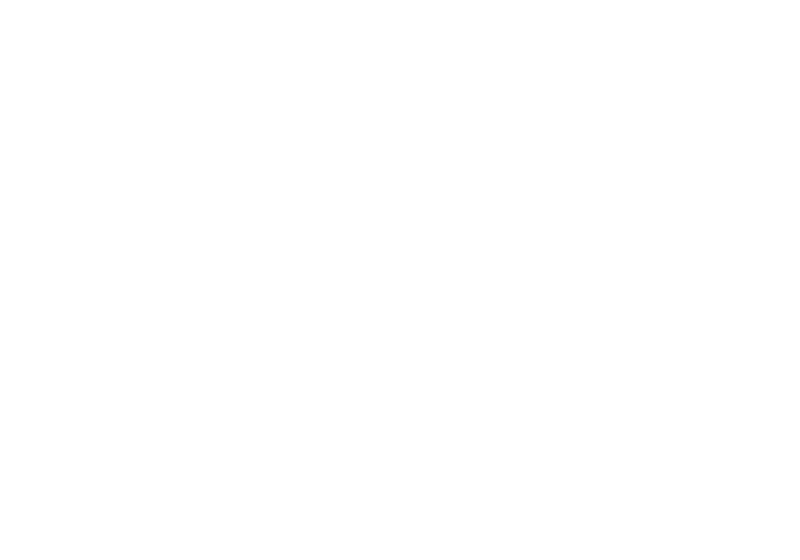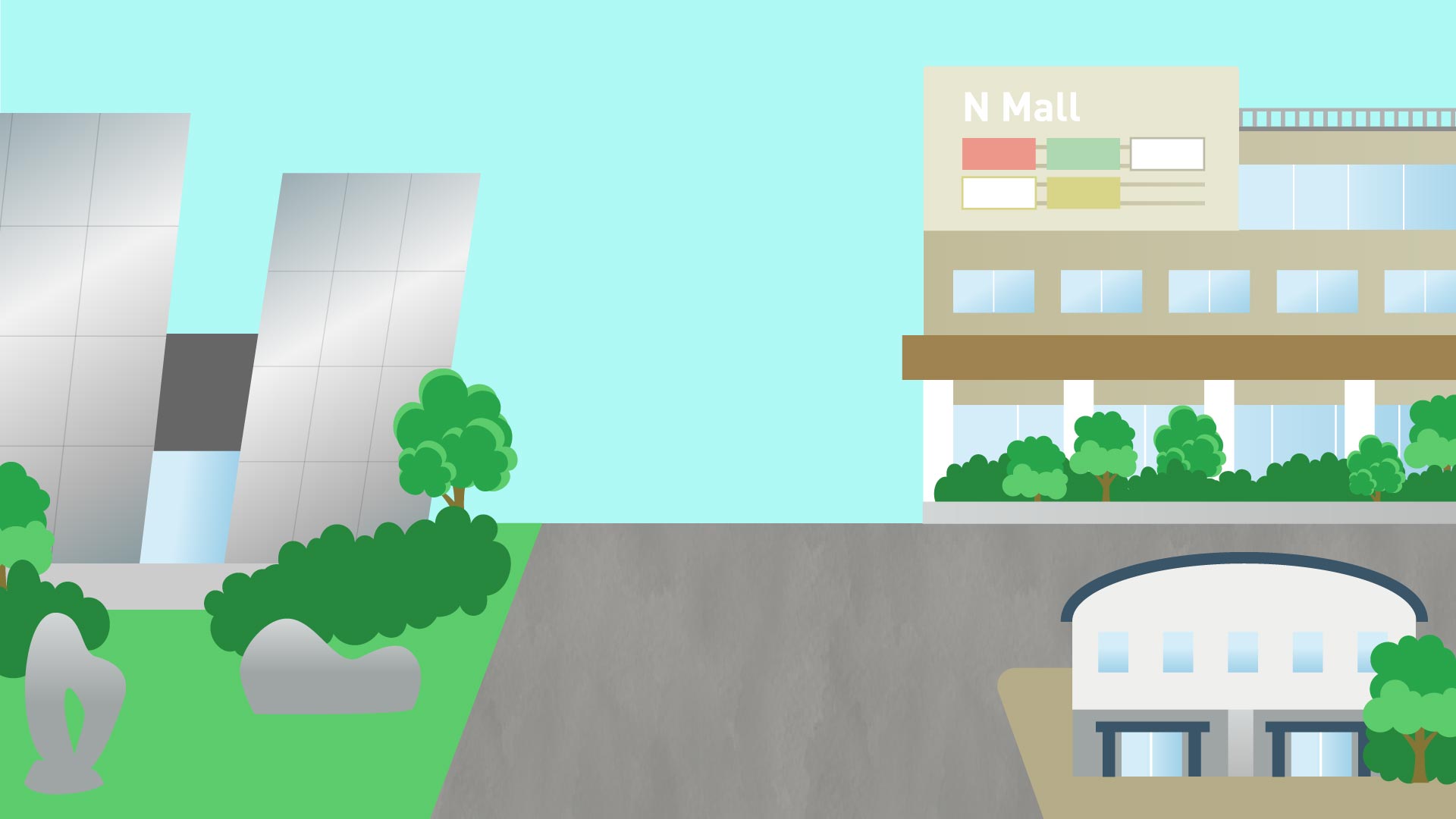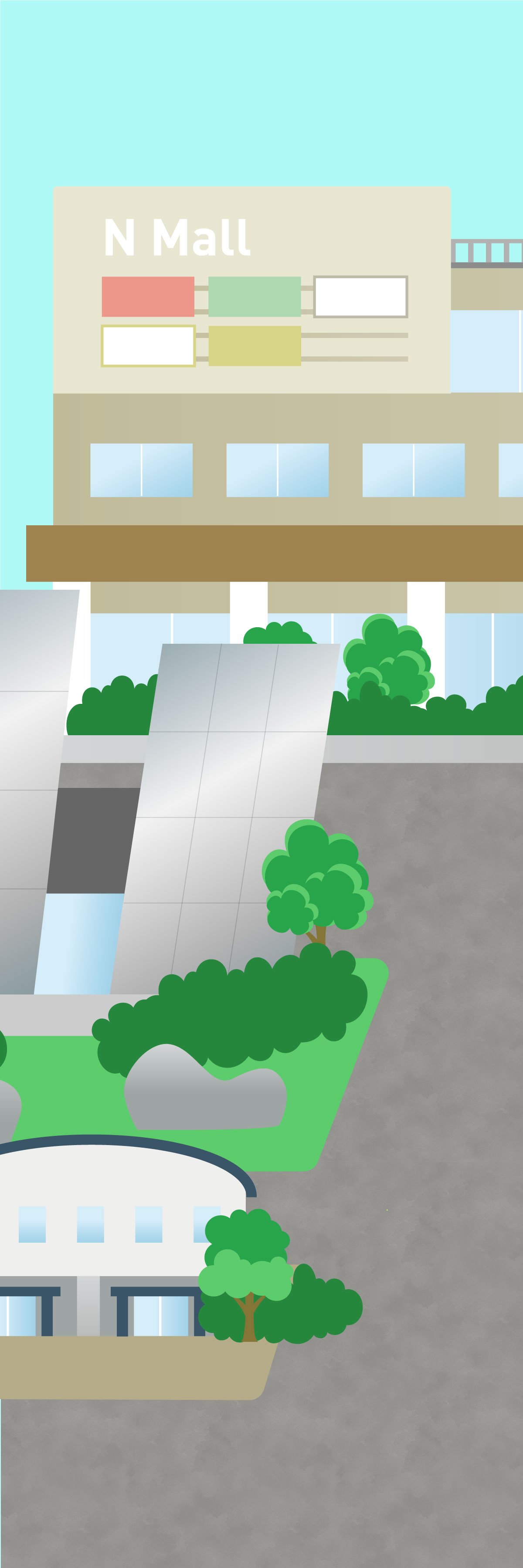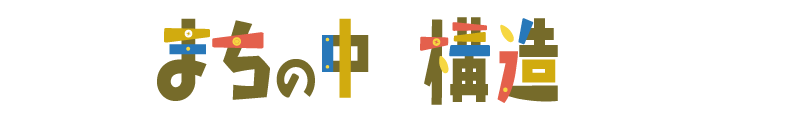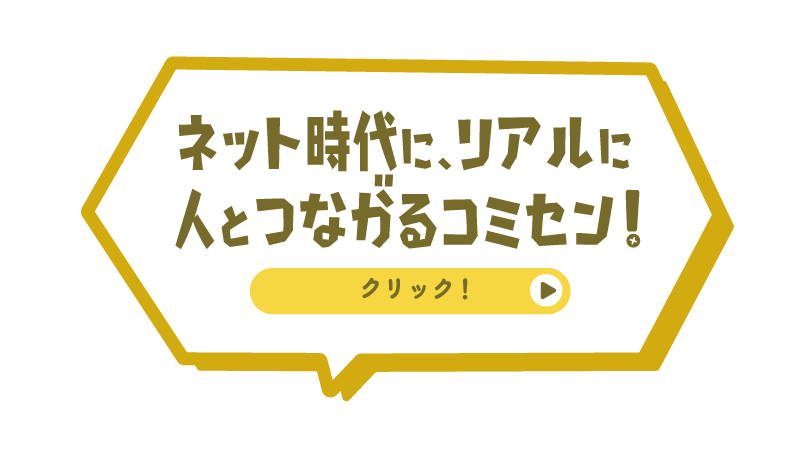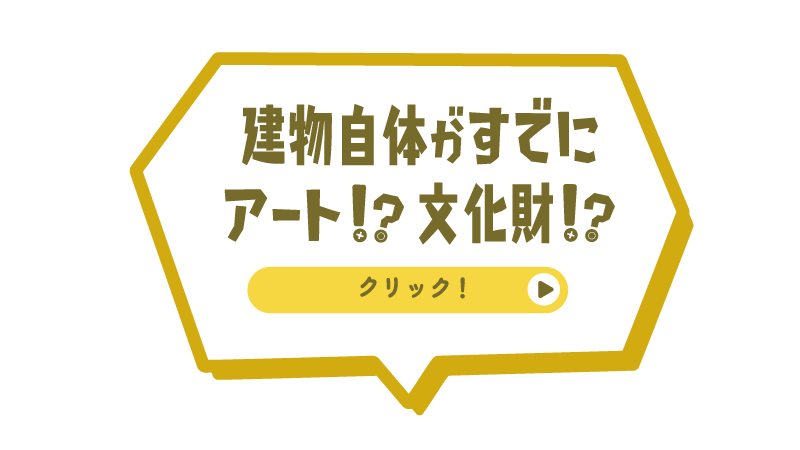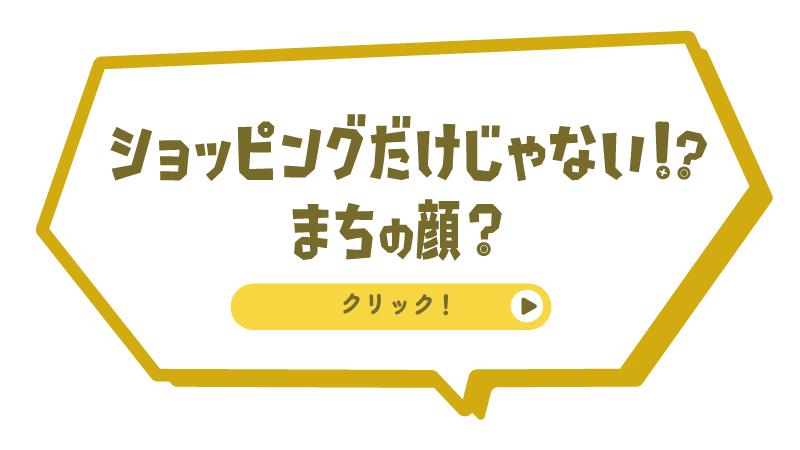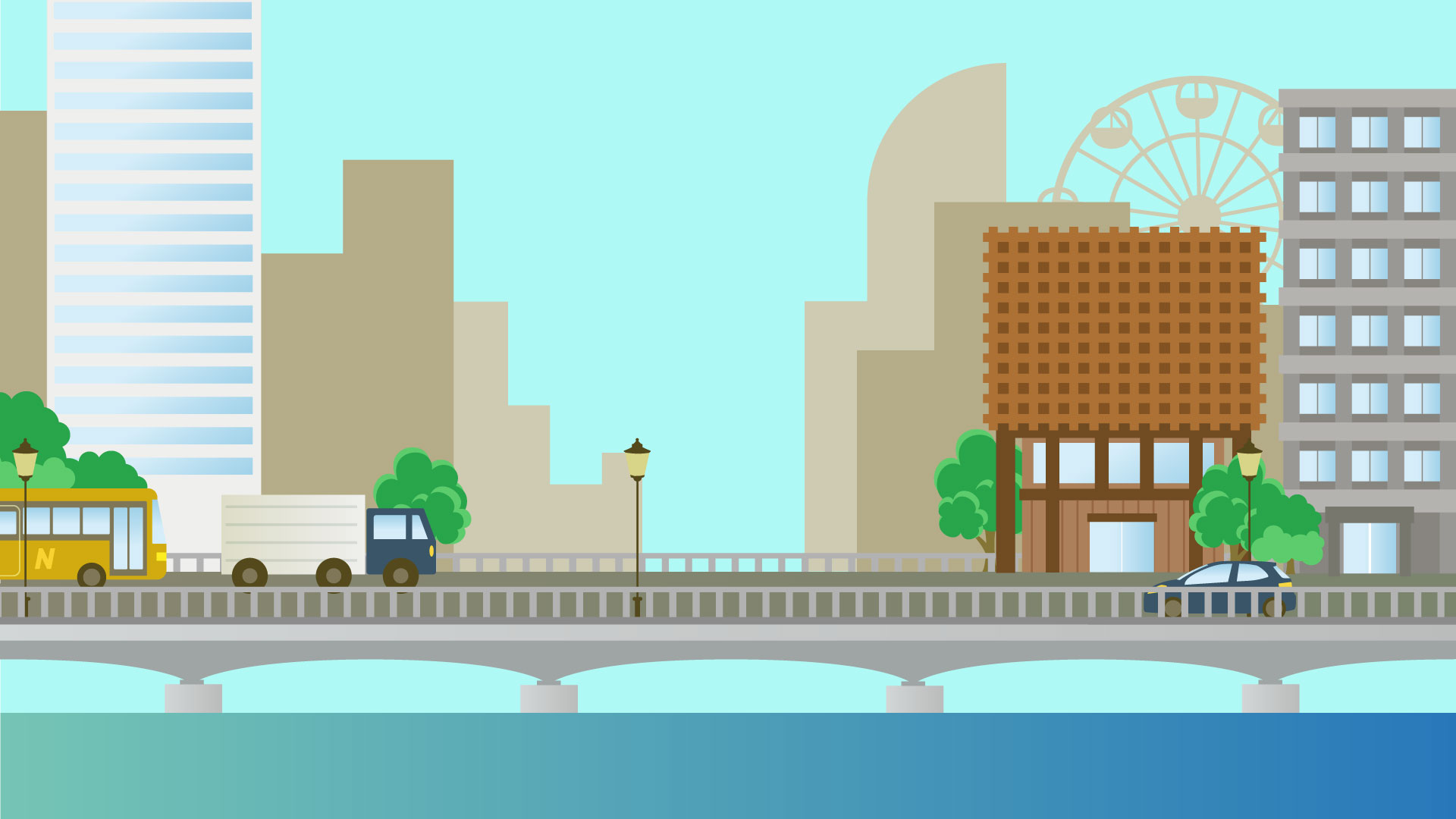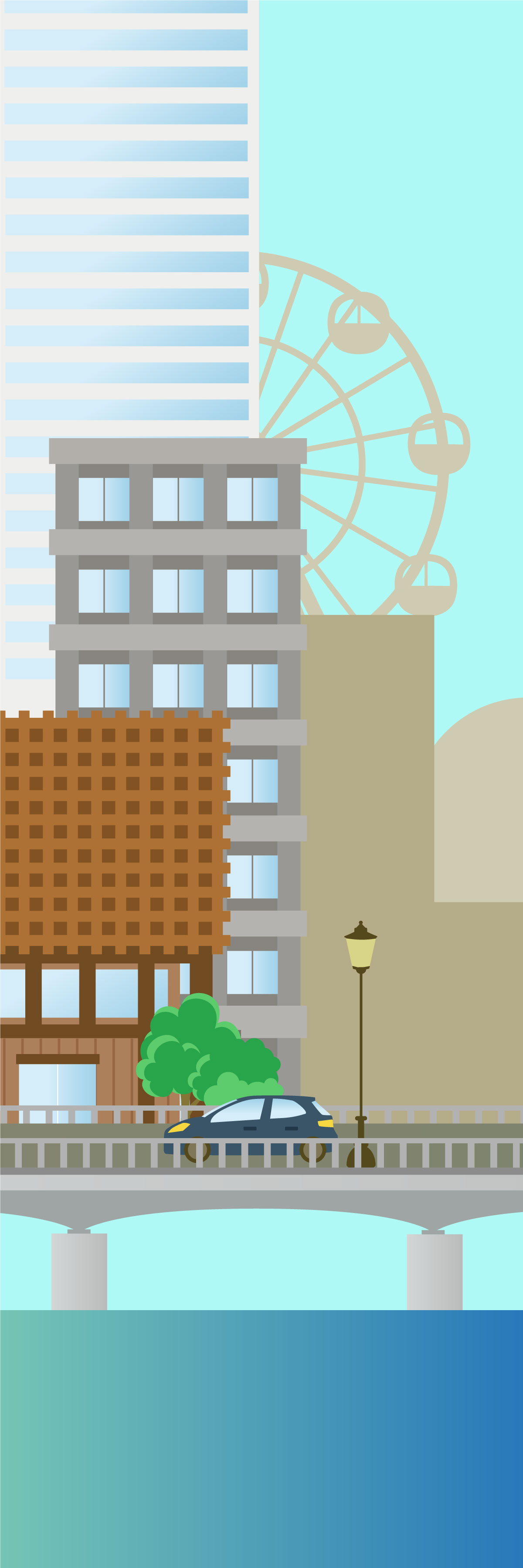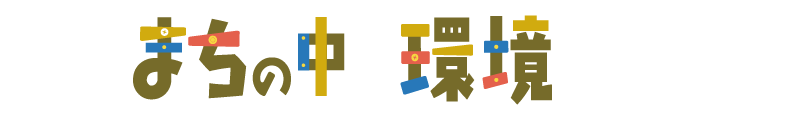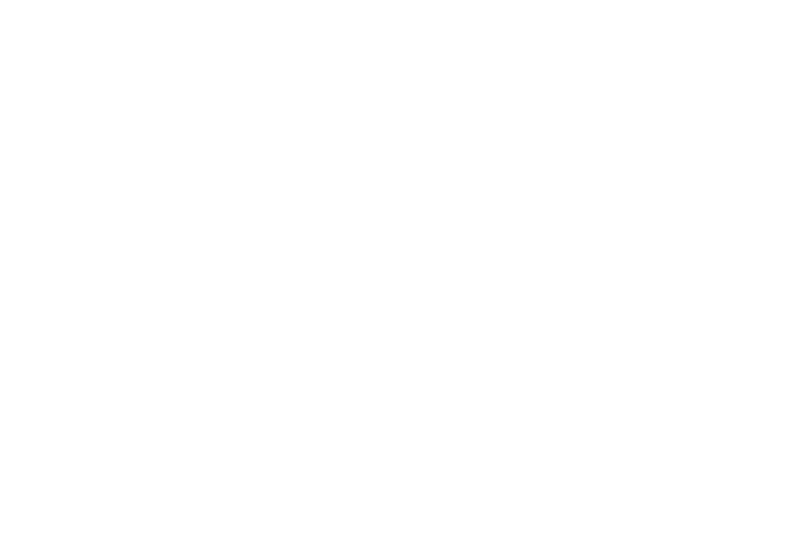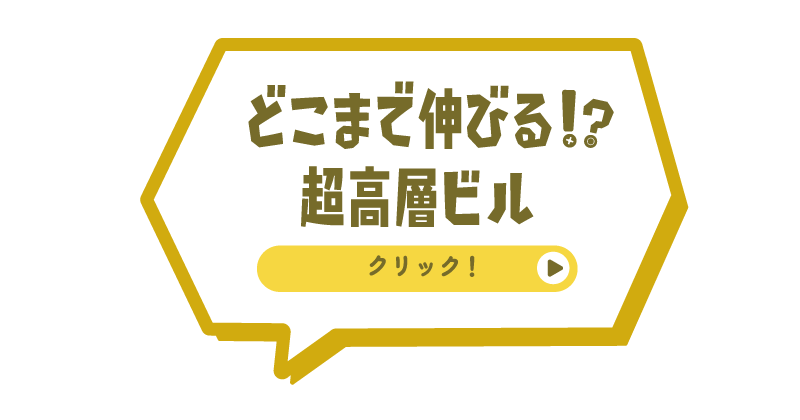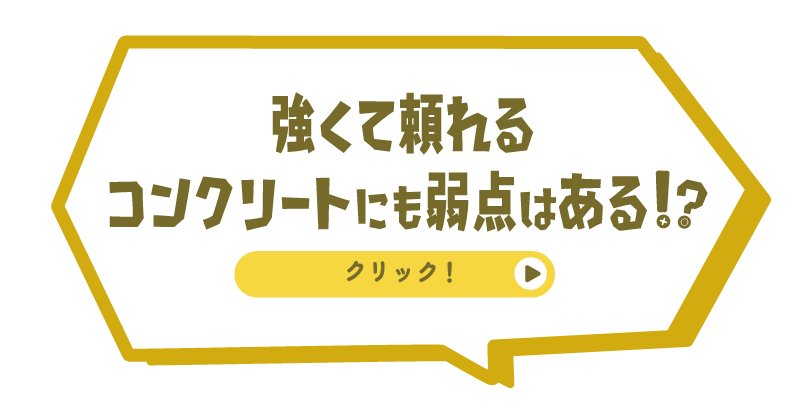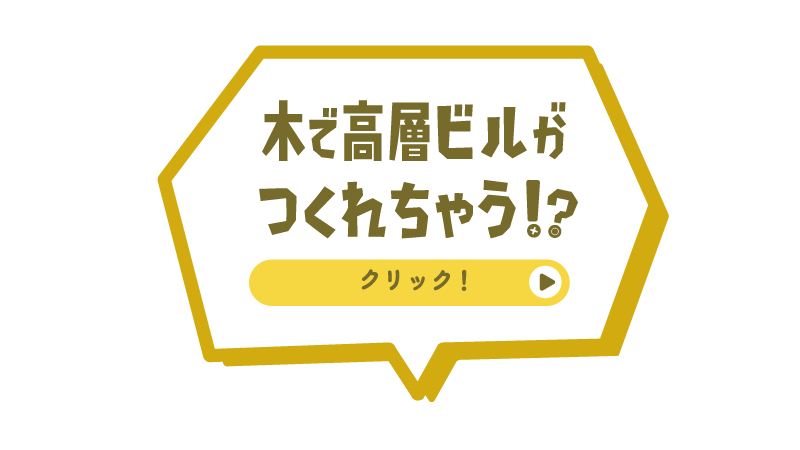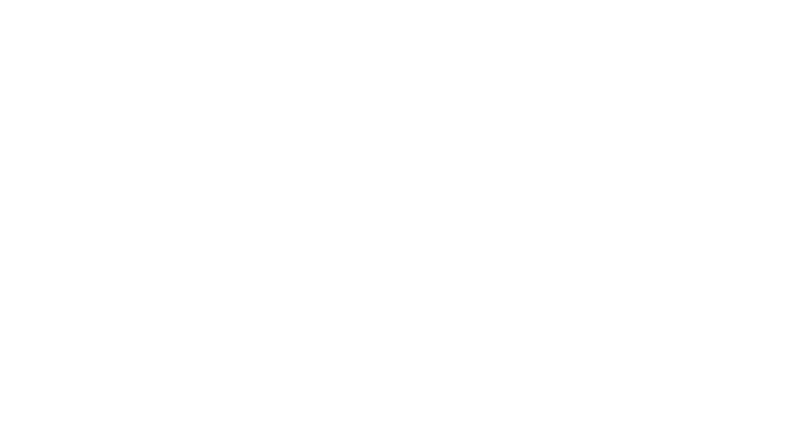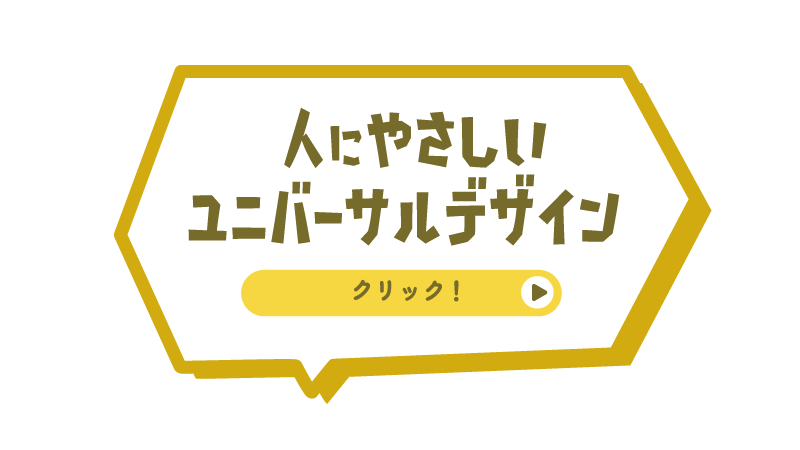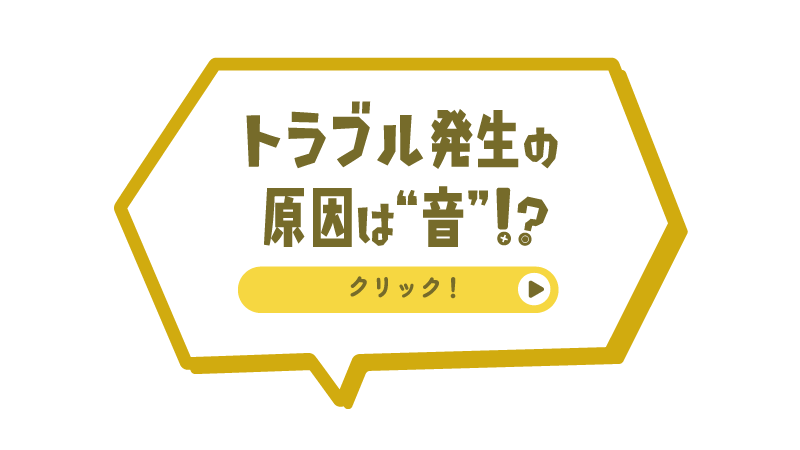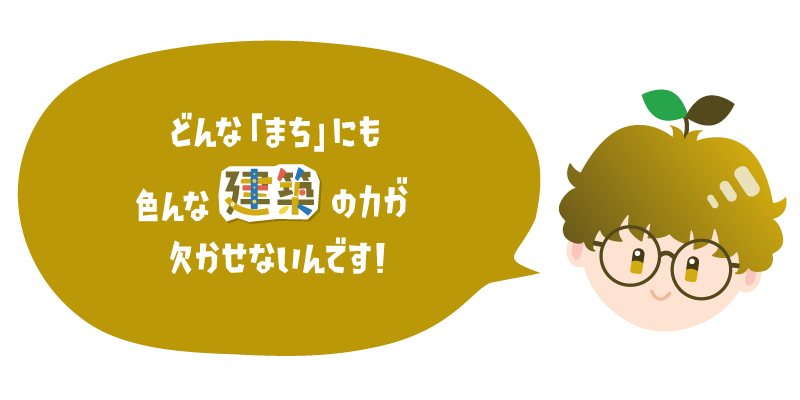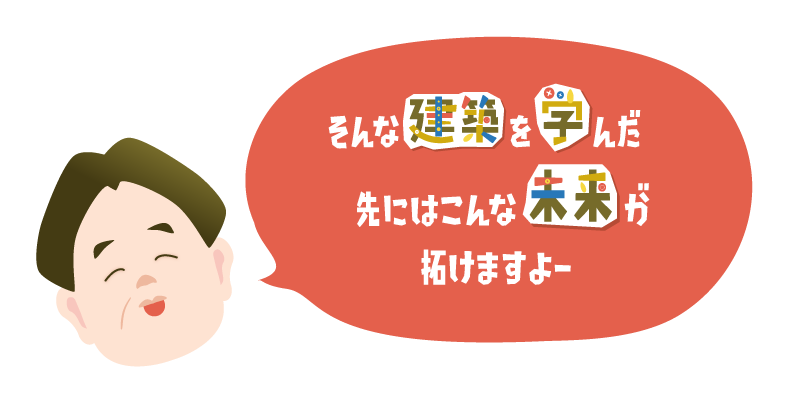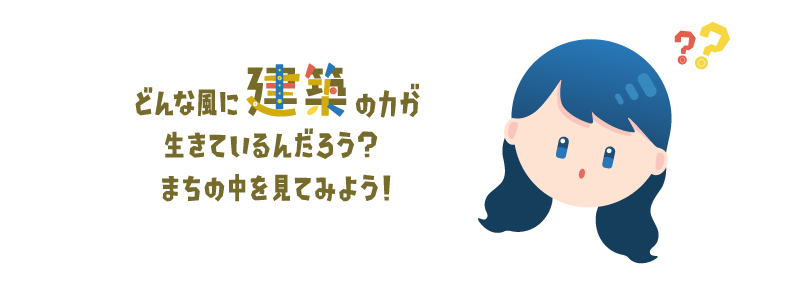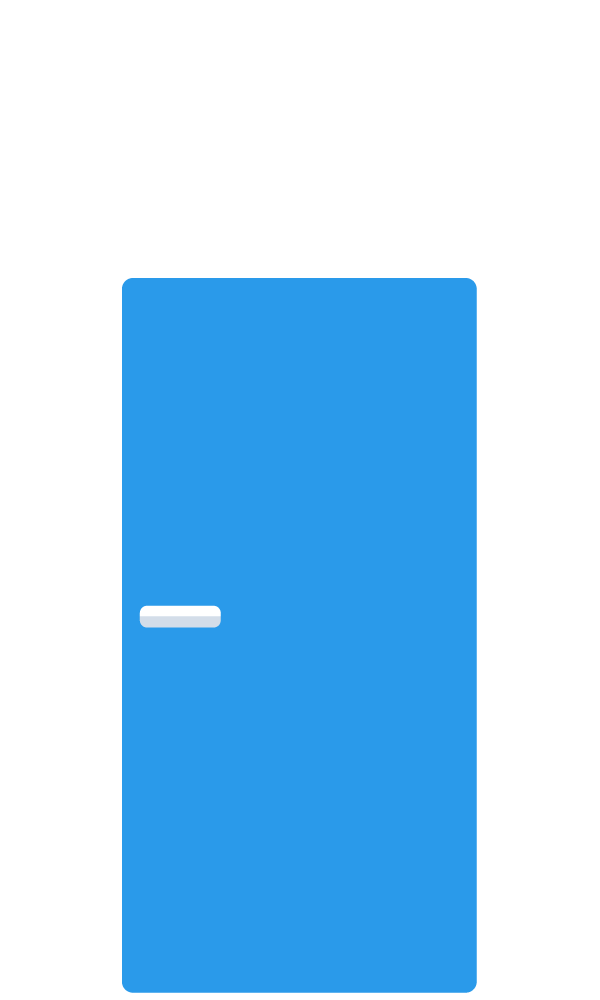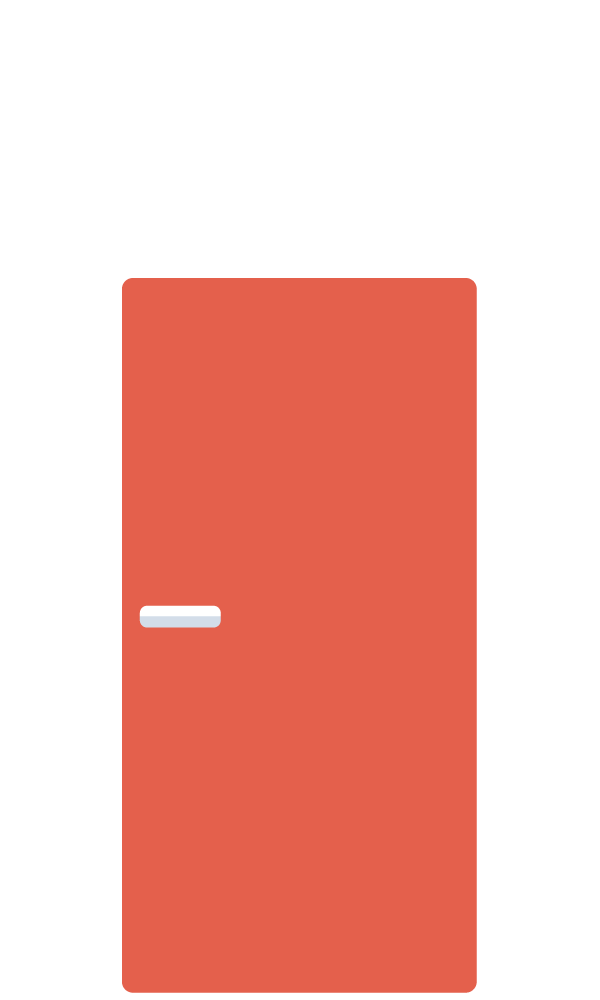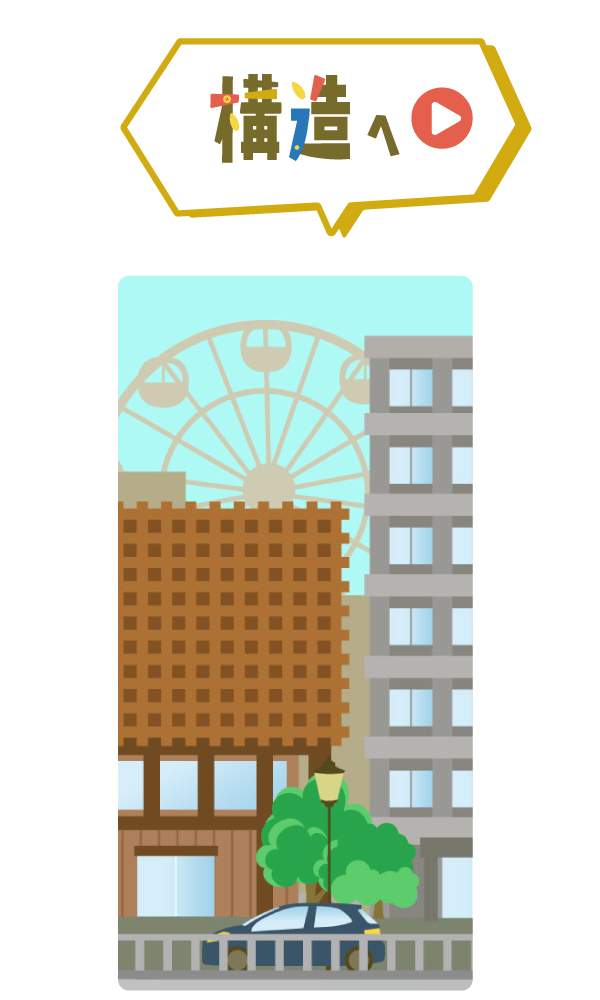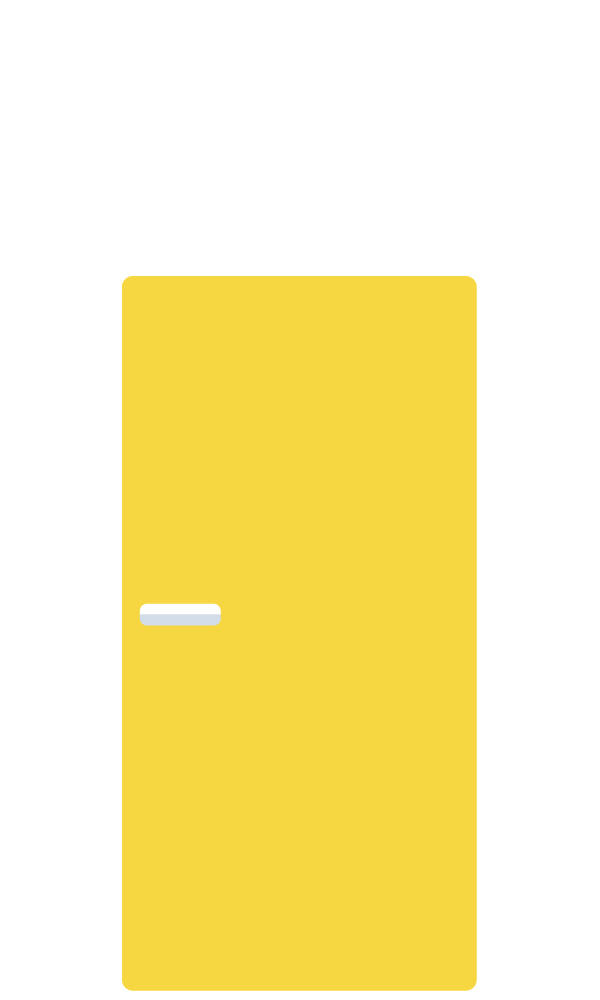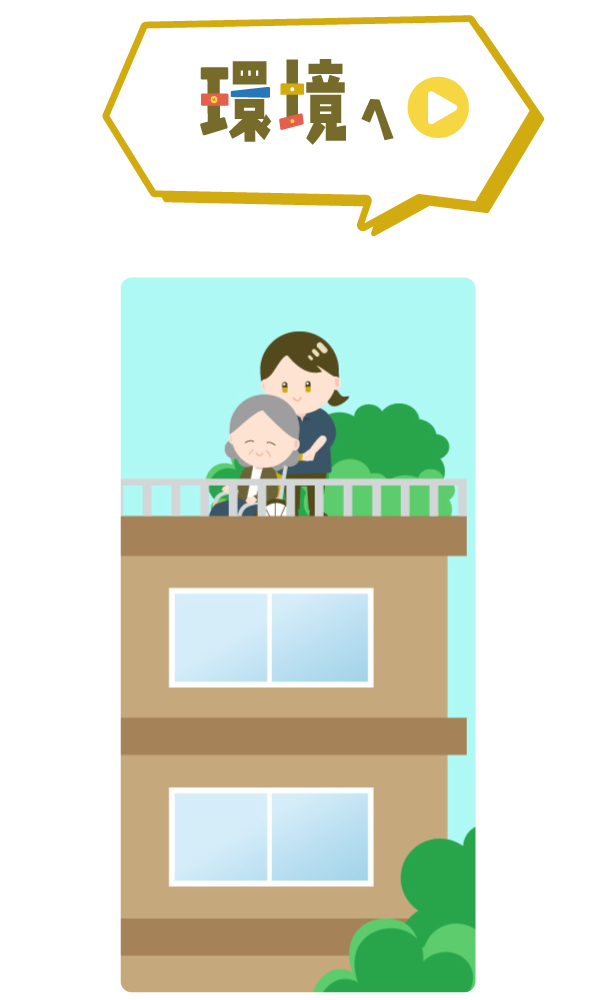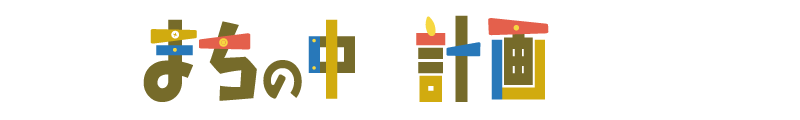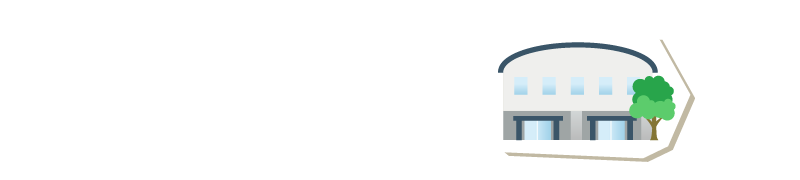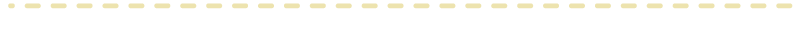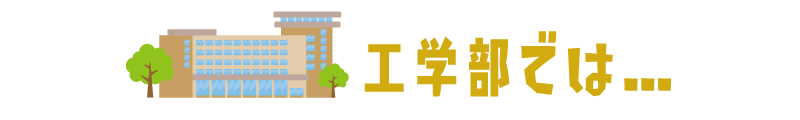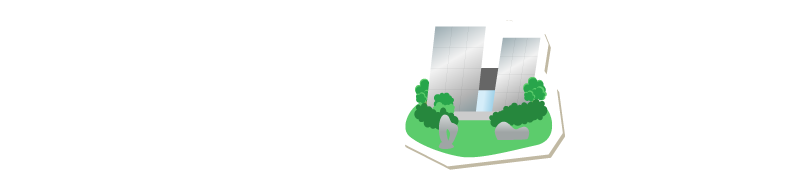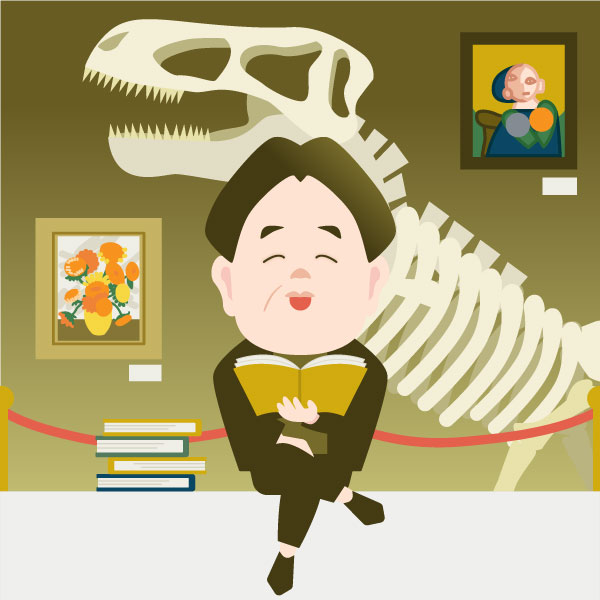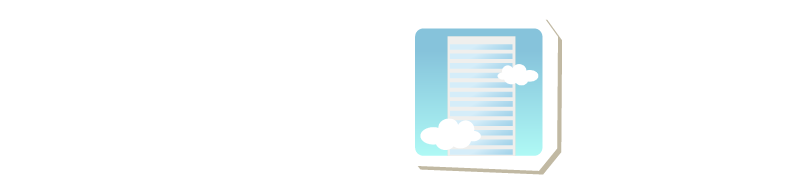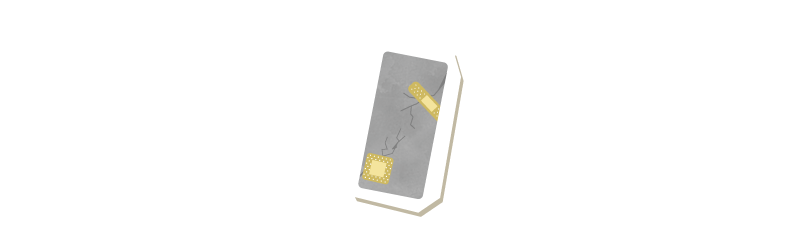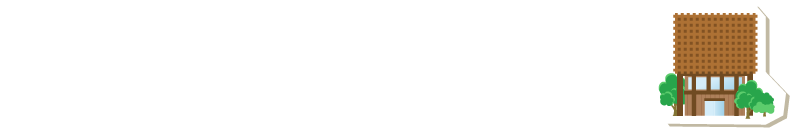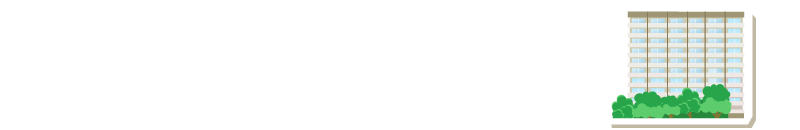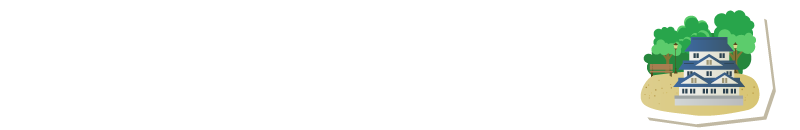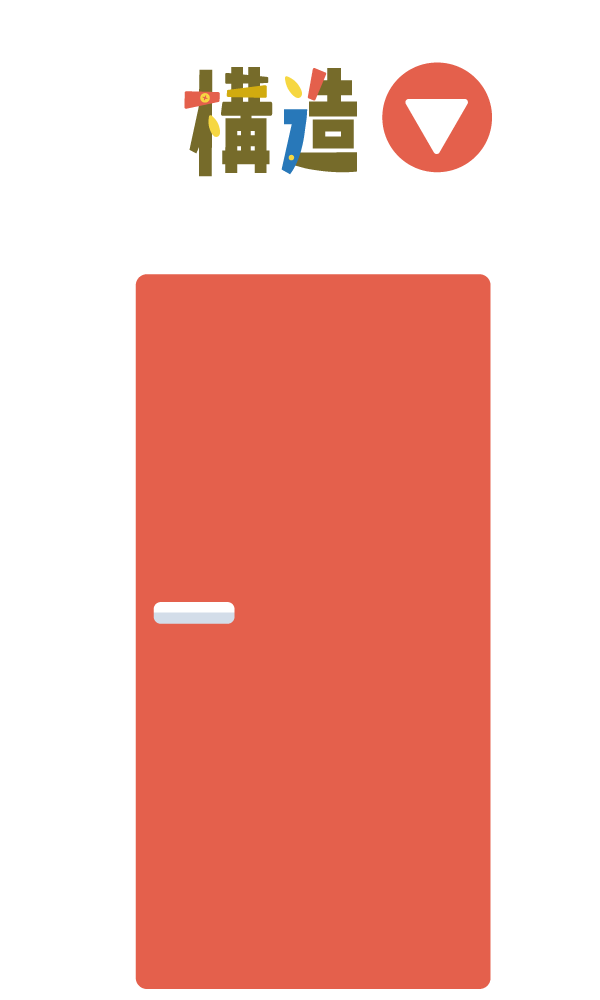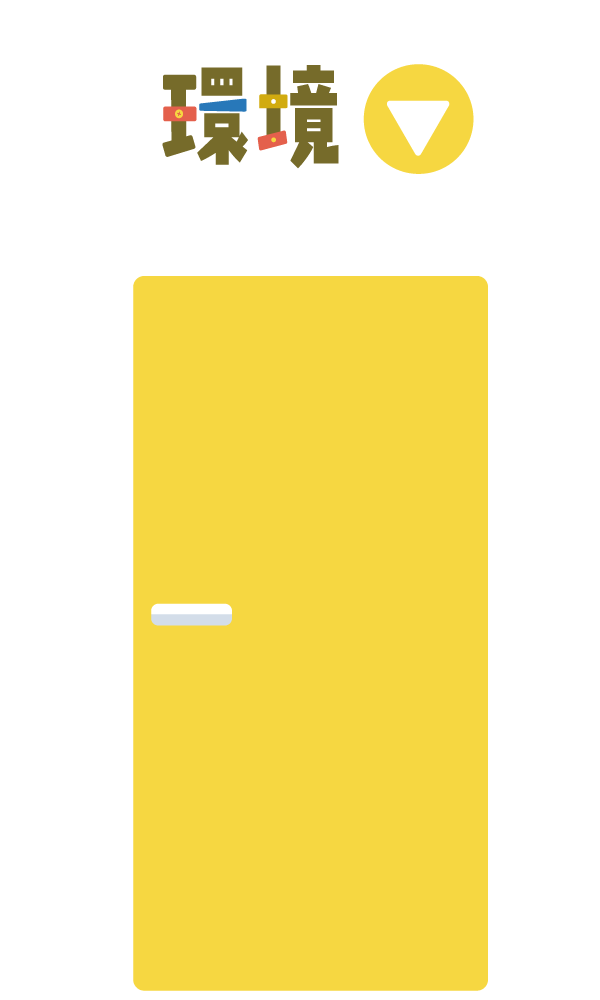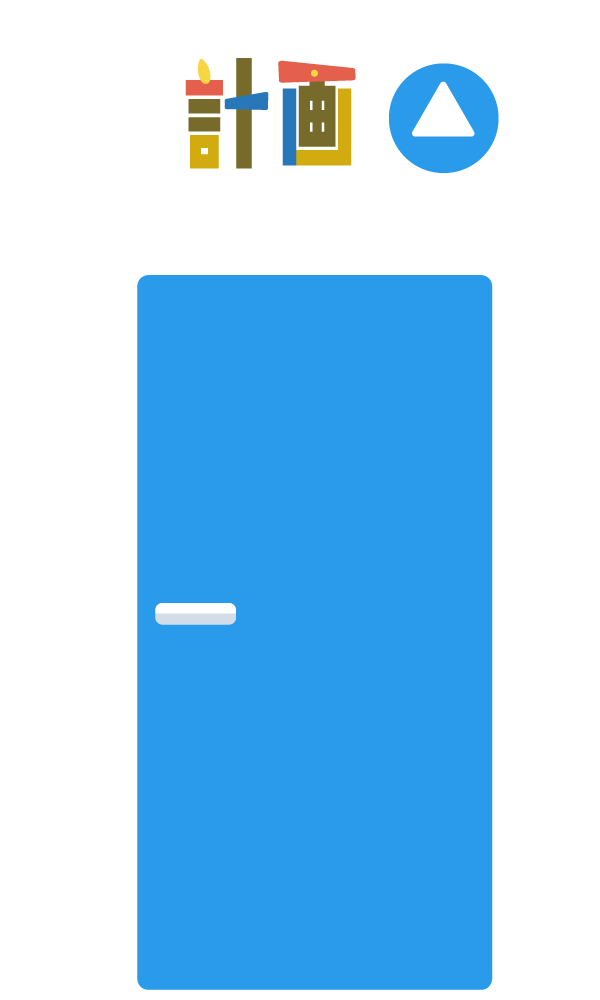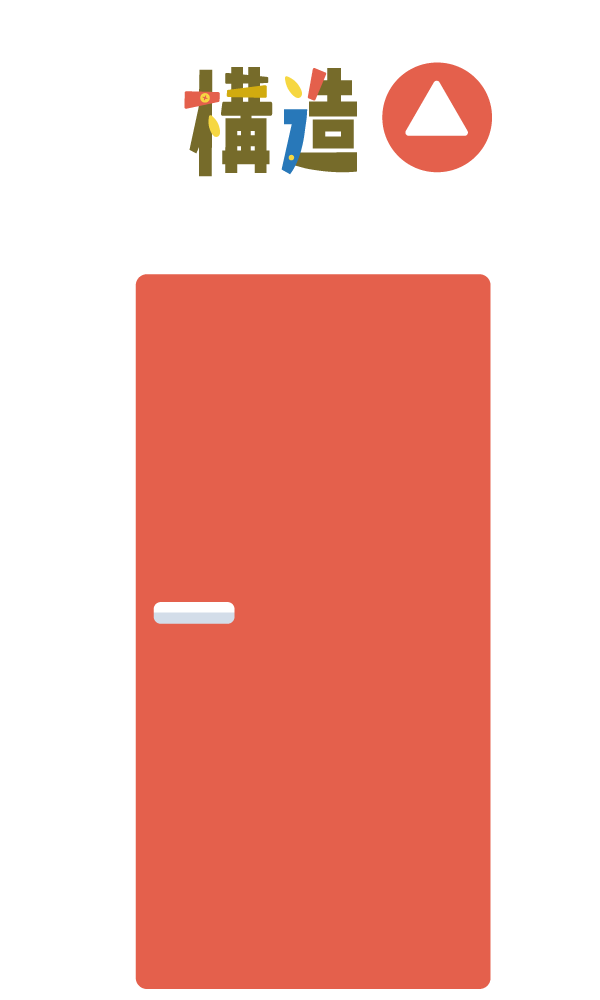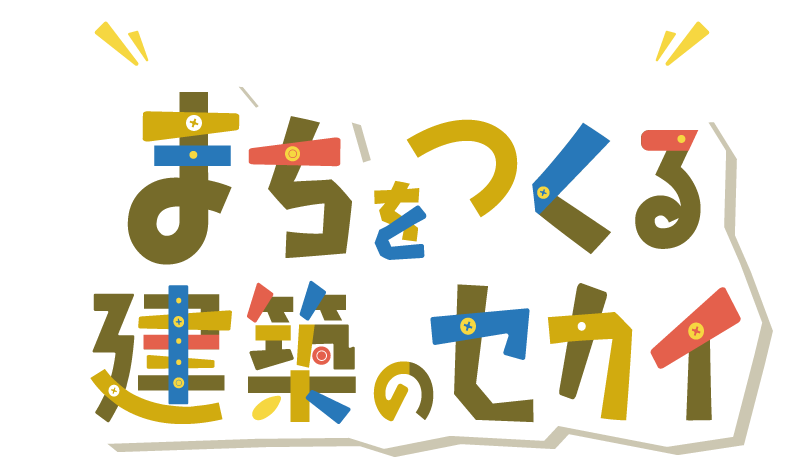
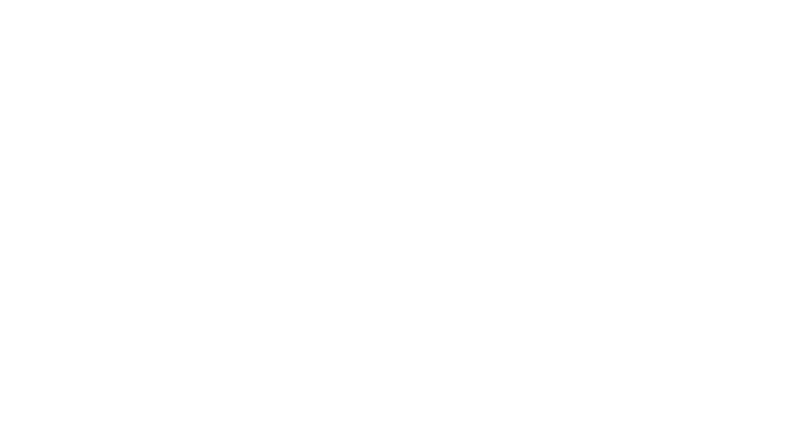
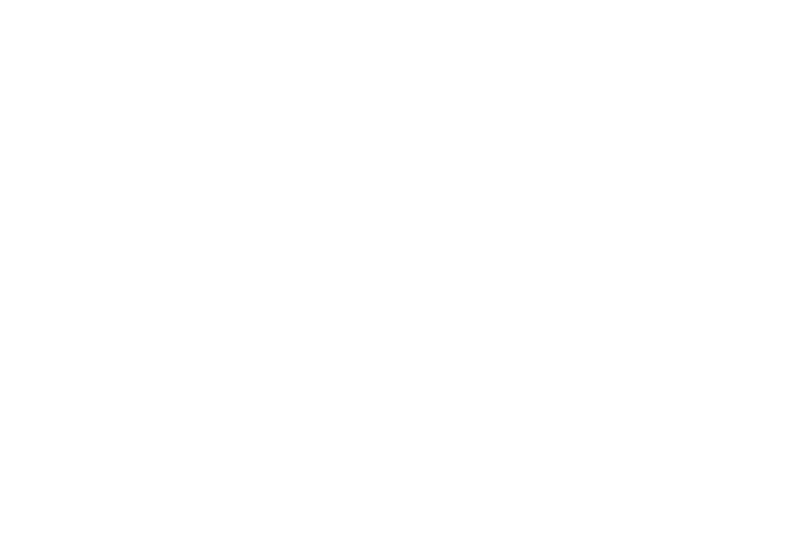
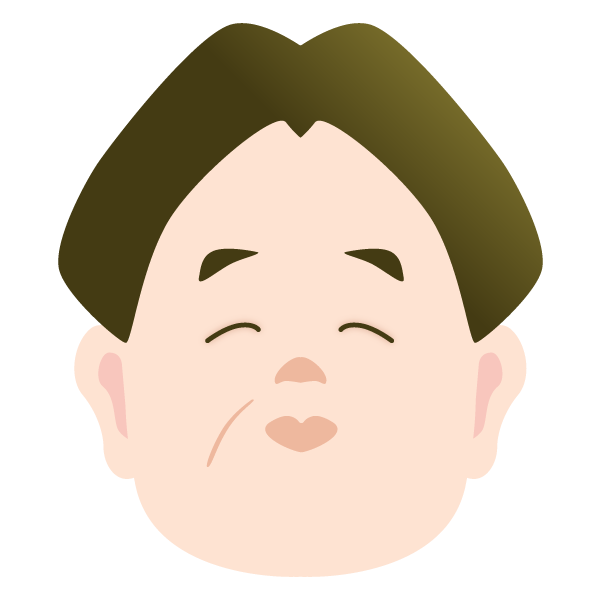

「建築学」の学びを極め、
大学で教授をしている


建築のセカイについて、
キョージュの元で勉強に励む大学生
頭の芽から花を咲かせることが目標


建築のセカイに興味があり、
日々身の周りにある建築について
探究する、好奇心旺盛な高校生