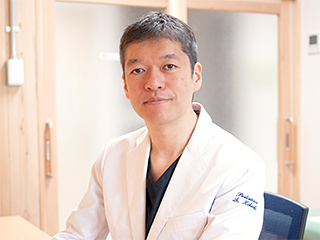2020-07
ロハス工学ヘルスケアデータ解析プロジェクト

ロハス工学の視点から人々の健康を見守るまちづくりを目指す
概要
スマートウォッチなど家庭でも使える生体情報測定デバイスが普及し、個人が容易にヘルスケアデータをウェブ上に蓄積できるようになりました。この流れは新型コロナウィルス感染症の流行により急速に加速され、医療やヘルスケア分野が飛躍的な発展を遂げると期待されています。一方で、家庭などで蓄積された膨大なヘルスケアデータをどのように分析し活用するかは今後の課題であり、特に疾病リスクを発見した後に必要となる行動変容(生活習慣を変える)のための原動力となるようなデータ提示方法については効果的な方法が見いだせずにいます。こうした課題に取り組むため、私たちは医療とヘルスケアの専門家に加え、人工知能やデータ分析の専門家とともに「ロハス工学にもとづく発想でヘルスケアの未来を創造する」ロハス工学ヘルスケアデータ解析プロジェクトを立ち上げました。ロハス工学の視点から人々の健康を見守るまちづくりを目指します。
◆研究内容
新型コロナウイルス感染症が流行したことにより、私たちはこれまでになく頻繁に体温を気にして、測定するようになりました。毎日体温を測定して体調に意識を向けていると、ほんの少しの体調の変化に気付くことがあります。このように、「自分が知っている自分の体調の変化」を数字にして記録すると、不調の際には自ら適切な対応ができるようになります。この毎日の体調記録のことを、ヘルスケア・データログ、省略して「ヘルスログ」と言います。将来には、かかりつけのお医者さんともヘルスログを共有することで、より適切な医療を受けられるようになると期待されています。
ヘルスログは体温だけではありません。様々なウェアラブルセンサが開発され、心拍数や呼吸数、血中酸素飽和度、血糖値、歩数、運動量などを、スマートウォッチを身につけるだけで測定できるようになりました。さらには、IoT(モノのインターネット)技術と繋がることで、これらの生体データが自動的にウェブ上に記録されるようになりました。これに加えて、毎日の日記や、イベント、食欲や寝付き、そして学校や職場で記録される身体測定値、体力測定値、ストレスチェックなども含めると、私たちの健康に関するありとあらゆる情報が点在しているといえます(これらを総称して、ライフログと言います)。
さらに想像を膨らましてみましょう。近い未来には、これらのライフログが何万人、何億人分もウェブ上に記録されるようになります。この巨大で複雑なデータのことを、ビッグデータと言います。ビッグデータの海のなかを、人工知能の力を借りて泳ぐ(解析する)ことで、特定の人(例えばあなた)の、今の生活を続けた先の未来(生活習慣病発症のリスク予測など)が正確に行えるようになるでしょう。自分の未来の姿を見てしまうことは、自分を律する気持ちが高まり、生活習慣を変えるなどの行動変容のきっかけになるかもしれません。あるいは、データに翻弄されて不安ばかり増えてしまうかもしれません。
いずれにしても、ヘルスログやビッグデータは、知識だけでは無く人の心や感情にも影響を与えることになるでしょう。
生活習慣を変えようと努力したり、肥満を解消しようとダイエットを続けていても、毎日の努力はすぐには数値として表れず、長期的に続けて始めて効果が現れます。継続して努力するためには、この、ほとんど誤差のような目には見えない毎日の積み重ねを「大切だと思えるかどうか」「面白いと思えるかどうか」が大切なのでしょう。実は、このことは健康だけに限らず、省エネやSDGsを意識した行動や、勉強の積み重ねにも同じく言えることです。私たちロハス工学ヘルスケアデータ解析プロジェクトは、この「塵も積もれば山となる」を実践するロハス工学にもとづく発想で、新たなヘルスケアデータ解析の方法を研究します。
ヘルスログのビッグデータを味方にして、工学部の学生達、地域の人々を日本一元気にすることを目指します!
◆研究活動の概要
令和4年度より基礎体温のビッグデータ解析にターゲットを絞り、工学部のメンバー(データ分析(2名)、データ評価(2名)、およびデータ収集(3名))に加えて、データサイエンスが専門の日本大学生産工学部・豊谷純教授、植村あい子助教との連携を進めています。加えて、基礎体温ビッグデータを有するキューオーエル株式会社(代表取締役・北沢眞澄)からデータ共有の承諾を得て、工学部、生産工学部、キューオーエル株式会社の間で3者間共同研究契約を締結しました。さらに、プロジェクトメンバー外のアドバイザーとして早稲田大学客員教授・戸川達男先生、庄司産婦人科・谷内麻子医師にご協力いただける体制を構築して研究を進めています。令和5年度には、下記2件の研究結果を内容を取り纏めて論文として発表しました。
1.装着式衣服内温度計を用いて測定した腹部皮膚体温が月経排卵周期とともに二相性を描き、排卵日の推定に有用であることを示しました。
Yoshinobu Murayama,Masumi Kitazawa,Hiraku Sato and Aiko Uemura,”The accuracy of abdominal skin temperature in detecting ovulation compared to basal body temperature.” Japanese Journal of Applied IT Healthcare,vol.17,Issue suppl2,pp.6-9,2022,DOI:10.11204/ithc.17.s2_6
2.衣服内温度を用いた就寝時腹部皮膚体温のゆらぎ成分が、卵胞期、排卵期、黄体期に応じて変化することを示しました。
Yoshinobu Murayama,Aiko Uemura,Masumi Kitazawa,Jun Toyotani,Asako Taniuchi and Tatsuo Togawa,”Determination of biphasic menstrual cycle based on the fluctuation of abdominal skin temperature during sleep.” Advanced Biomedical Engineering,vol.12,pp.28-36,2023

学生たちの協力によるアンケート集計

データ解析用プログラムの開発

社会実装に向けたSmart Wellness Town PEP MOTOMACHIプロジェクトとの連携
プロジェクトメンバー

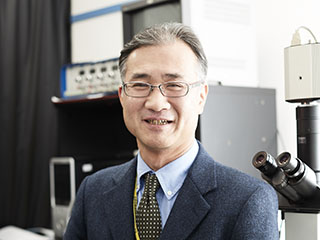


身体測定
保健室/看護師
高橋 秀子(看護師)