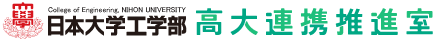2024.10.22
ロハス探究
郡山ザベリオ学園中学校の総合探究学習として「ロハス工学学習」の成果発表会が工学部にて行われました

9月10日(火)、郡山ザベリオ学園中学校の約50名の生徒が工学部に訪れ、62号館3階にあるAV講義室にて、ロハス工学学習の成果発表会が行われました。郡山ザベリオ学園中学校では総合的な探究学習の一環として、土木工学科の岩城一郎教授らによるロハス工学学習の特別授業を行っています。現3年生が1年生の時に工学部キャンパスを訪れ、岩城教授の講義を聴き、「ロハス工学とは何か」を学ぶとともに、健康と環境、持続可能な社会を心がける生活スタイルを実践するために、「緑化」、「アクアポニックス」、「コンポスト」、「インフラ」をテーマに、7つの班に分かれ、自分たちでできるロハス活動について考えました。ファシリテーターとして、岩城教授をはじめ、土木工学科の中野和典教授、小児科医院の菊池信太郎院長、工学部研究員の浅野和香奈氏、石橋奈都実氏が活動を支援しました。いよいよ3年間に及ぶ活動の成果を発表する日が訪れました。先生方を前に、生徒たちは少し緊張しながらも、大学生も顔負けの堂々としたプレゼンテーションを披露してくれました。

CO2を吸収し地球温暖化対策などのSDGsにつながると考え緑化活動に取り組んだ1班。ポンプを利用せずに、畑よりも高い場所で雨水を集め重力エネルギーを使って水を撒く方法も考案しました。コンポストメンバーと一緒に約70種類の植物を育てる中で、人間と同様に植物も日々気遣いすることが大事だということを学びました。

アクアポニックスは魚の養殖と水耕栽培を掛け合わせた循環型農業。2班では工学部を訪問したり小学校の先生にインタビューし、農薬を使わずゴミを出さない持続可能なアクアポニックスの運用方法について、詳しい知識を修得。試行錯誤しながら第1号・2号・3号を制作し、改善点を次の装置に活かすPDCAサイクルも実践しました。

学校のゴミを減らしたいと考えコンポストを作成し、落ち葉やコピー紙を利用して栄養豊富な肥料にした3班。チームワークを育みながら、学校で出るごみの種類を知り、肥料づくりの知識を得ました。また、コピー紙を粉砕して和紙作成にも挑戦。今後もロハス学習を通して学んだことを活かして、視野を広げていきたいと考えています。

5・6班は工学部を訪問した際、橋梁の整備方法や仕組みについて詳しく知りたいと考えたことがきっかけで、インフラ整備に取り組みました。模型をつくって橋の構造を理解したうえで、日大工学部考案の橋ログアプリを使って学校周辺の2つの橋を点検。 情報化された橋の劣化データに基づき、清掃を中心としたメンテナンスを実施しました。

科学的に心が明るくなると証明されている挨拶で全校生徒の心を健康にすることを目指し、校内に「あいさつロード」を設定した7班。実施前は3割程度だった挨拶の割合が実施中は7割になり、実施後のアンケートでも8割近くの人が挨拶されるといい気持ちになるといった、心の健康度合いが向上。全校生徒が健康になったと実感できました。

4班では、ロハスを知り、健康と環境にやさしい生活を送ってもらうために、さまざまなツールを利用した活動を展開。ミニクイズを盛り込んでロハス活動を紹介するポスター、遊びながらロハスを身近に感じてもらうロハスすごろく、ロハスや活動を紹介するパンフレット、HP掲載用の動画も作成。地球のためにも、もっとロハスを広めていきたいと思いました。
全班の発表後には、活動を支援してき先生方が講評を述べました。中でも先生方が絶賛されたのが、パワーポイントのクオリティを含めたプレゼンテーションの高さでした。テーマは違えど、ロハス活動を通して自分たちで課題を発見し解決方法を見いだし、実践した結果について検討、さらに今後どうするかを考えるPDCAプロセスは、大学の研究活動に通じるものであり、「チームで協力して取り組んだ経験は人生において大きな財産になる」と頑張った生徒たちを称賛しました。最後に岩城教授は「これからもロハスに対する意識を持ち続けることが大事」だと伝えました。
生徒たちからは、「素晴らしい先生方に出会えたことが私たちの財産」という気持ちを込めて、「ありがとうございました」の感謝の言葉をいただきました。

発表を終え緊張から解き放たれた生徒たちは、大学生気分を味わいながら学生食堂での昼食を楽しみました。その後、新たに設置されたロハスの森「ホール」を見学。岩城教授は、ロハスの森の前身であるロハスの家群の紹介、令和元年東日本台風による被災後の跡地再生の道のりについて説明し、建築学科の髙木義典研究員は木材を活用したロハスの森「ホール」の設計や地下水を利用といった設備の特色について紹介しました。中野教授からチガヤを使った遮熱屋根の構造やアクアポニックスの計画について説明後、屋外に出て「ホール」全体の構造を見ていただきました。最後に記念撮影して、工学部でのロハス探究活動の授業終了となりました。


ロハスを学んだ生徒のみなさんから寄せられた声
- ロハス探求の活動から視点が広がり、今後にも生かせると思います
- 水を循環させて無駄にしないアクアポニックス。植物を育てることで心も癒されます
- ロハスはSDGsよりも具体的な行動につながる印象が強く、魅力を感じました
- 自分たちで主体的に行動したことが、いい経験になりました
- 最初に体験した探究授業がロハスでよかったです
- 大学は中学校とは違って、自分のやりたいことができる場所なんだと感じました。僕も学んでみたいと思いました
- ロハスが持続できるように後輩たちにも伝えていきたい
- 雨水を集めて花壇で植物を育てる活動を通して、SDGsやロハスに貢献できたかなと思います
- ロハスを学んで新しいものの見方を知ることができ、とても役に立つ授業でした。この学びが将来、大学での学びにつながっていくんだと実感しました
これからの時代を担っていくみなさんが、きっと人と環境にやさしい持続可能社会を実現してくれることでしょう。学んだことを糧に、みなさんが今後益々成長されることを期待しています。